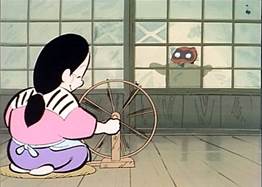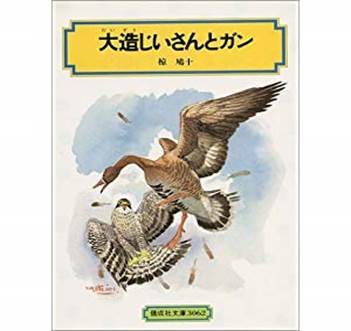|
�Q�O�P�U�N�x���ʃR�����u�����ǂށv |
|
|
|
�����ǂ��@ ���P����u���ʂ��̎��ԁv �@ �P�X�Q�W�N�A���\�A�A���V�A�̘̐b�����Ƃł���u�E�v���b�v�Ƃ����l���A�w�̘b�̌`�Ԋw�x�Ƃ��������ŁA�S�Ă̘̐b�ɂ͋��ʂ���\���A�����܂�̃p�^�[��������Ƃ������\���A���̍\�����O�\��̋@�\���ނƂ��Đ������܂����B�ȒP�ɗ��Ă݂�ƁA�@�N���̕s�� �A�֎~ �B�֎~�̐N�� �C�G�ɂ��T�� �D���̘R�k �E�G�̛@�v �F�s�{�ӂȗ��G�s��
�G�G����̉��Q�A���͉����̌��� �H��l���ւ̒���@�I�����̎n�܂� �J��l���̏o�� �K���^�҂̓������� �L����ɑ����l���̔����@�M���@�E��i�E����̎擾
�N��l���̈ړ��@�O�G�Ύ҂Ƃ̓��� �P��l��������� �Q���� �R�s�K�܂��͌����̉� �S��l���̋A�� ㉑��l�����ǐՂ����@㉒�ǐՎ҂���~���� ㉓��l���������ɓ����@㉔�U��l���̉R�̎咣
㉕���@㉖���̉��� ㉗��l�������ʂ����@㉘�U�҂̔��o�@㉙��l���̕ϐg�@㉚�U�҂�G�̏����@㉛��l���̌����⑦���@�ƂȂ�܂��B ���̇@�`㉛�̋@�\���ނ́A�S�b�قǂ̃��V�A���b���璊�o���ꂽ���̂ł����A�S�Ă̘b���O�\��̋@�\�𑵂��Ă���̂ł͂Ȃ��A���̒��̊���ł��b���o���Ă���Ƃ������Ƃł��B����́A���E���̐_�b�E���b�ɂ����Ă͂܂�A���{�ł��A�܂��w�Î��L�x�̃��}�^�m�I���`�ގ���A�����Y�A�ꐡ�@�t�Ȃǂ̉p�Y����ɓ��Ă͂܂肻���ł����A����I�Ɍ����A�Y�����Y�₩����P�̕���Ȃǂɂ����Ă͂܂肻���ł��B�w�X�^�[�E�H�[�Y�x�ȂǁA����̏����E����E�h���}�E�f��E�Q�[���ɂ��A�v�������镔���������肻���ł��B ���ꍑ�ꋳ�ȏ��ɏo�Ă���w���ʂ��̎��ԁx�́A�u㩂ɂ��������K���A����̂����݂���ɏ�����ꂽ��A���̕s�ݒ��ɂ����݂���̐^�������Ď���a���A�����݂���ɉ��Ԃ�������v�Ƃ������b�ł��B���Ԃ��^����̈�ł��邱�̂��b���A�u�K���������������v�ɂ͇A�B���A�u�����݂���̐^�������ĒK�����a���̋Z�p��v�ɂ͇K�L�M���A�u����v�w���s�݂̓~�ɁA�K�����Ԃ��Ŏ���a���v�ɂ͇@��R���A�u�����݂���Ɍ������āA�K���A���Ă����v�ɂ͇S���A���Ă͂܂邩������܂���B �l�́A������ɂ��ė������铮���ł��B�O�\��Ɍ����Ȃ��Ƃ��Ă��A����Ɉ��̃p�^�[��������Ƃ������Ƃ́A���������̎d���������̃p�^�[���ɍi����Ƃ������Ƃł��B��葽���̕����m��Ȃ���A��葽���̗����̌^���g�ɂ��Ȃ��B������l�́A��������߂�̂ł��傤�B |
|
|
|
�����ǂ��A ���Q����u�X�[�z�̔����n�v
���ꋳ�ȏ��ɏo�Ă���w�X�[�z�̔����n�x�́A�u�����S���̑����ɏZ�ޕn�����r�����̏��N�X�[�z���A�a�l�̎�Â��鋣�n���ɗD���������̂́A�a�l�͖��ɂ���Ƃ����͎�炸�A����Ɉ����锒�n��D���A���̔��n���X�[�z�̂��Ƃ֓��S����Ă����ʎE����Ă��܂��v�Ƃ����߂�������ł��B�X�[�z�͎����n�̍������т��g���Ċy������A���ꂪ����ɂ܂Ŏc�郂���S���̔n���ՂɂȂ����Ƃ������ŁA���̕���͓���̒a��杂ɂȂ��Ă��܂��B ���V�A�l�u�E�v���b�v�́w�̘b�̌`�Ԋw�x�́A�̘b�ɋ��ʂ���\�����R�P�̋@�\�Ƃ��ĕ��ނ��܂������A������g���āw�X�[�z�̔����n�x�͂��Ă݂�Ƃǂ��Ȃ�ł��傤���B ����́A�X�[�z����ɂȂ��Ă��ƂɋA���Ă��Ȃ��A�܂��@�\�@�N���̕s���Ŏn�܂�܂��B�X�[�z�͎��������n�����Ȃ������q�n�������ĘA��A��A�厖�Ɉ�Ă�킯�ł����A�c��ȊO�ɉƑ��̂��Ȃ��ނɂƂ��Ĕ��n�́A�厖�Ȑg���ł���A�₪�Ă͗r��T�����鋭���ė��h�ȏx�n�ɂȂ�̂ŁA������@�\�M���@�E��i�E����̎擾�ɂ�����܂��B���N���o���A������X�[�z�͒��Ԃ�������a�l�̋��n���ɔ��n�Əo�ꂷ��悤�U���Ē��֍s���܂��B�D������Γa�l�̕P�ƌ����ł��܂��B���Ƃ��ƕn���������X�[�z�́A�@�\�G�]�������̌���������Ԃɂ���A���̒�Ăɏ��܂��B�@�\�H��l���ւ̒���I��l���̓��ӁE���� �J�o���������ɂ��Ă͂܂�܂��B�X�[�z�͒��֍s���A���n�ɏo�ꂵ�A�D�����܂��B�@�\�N�ړ��O�����Q�����ł��B�Ƃ��낪�A�a�l�̓X�[�z�̕n�����g�Ȃ������Ɩ�j��A��݂R���Ŕ��n��D���A��R����ނ�ł��̂߂��܂��B�@�\�G�G����̉��Q�ł��B���̌�A�X�[�z�͈�l�Ƃɖ߂�A���n���a�l����̓��S��}��܂��B�@�\�S�A�� ㉑�ǐ��ł��B�������A����A����ł��܂��܂��B�Ō�͔��n�����̐g������Ĕn���Ղ��X�[�z�ɍ�点�A�ނ͂����e���Ĕ��n���v���o���A�܂��@�\�R�s�K�܂��͌����̉��ŏI���܂��B ���̕���A���͕���ł��郂���S���ł͒m���Ă��܂���B��ґ�˗Y�O���̘b���������̖��b�W�́A�K�������ӎ����h�����鋤�Y��`�����̘̐b���W�߂ĕҏW���ꂽ���̂ł��B�ꌩ������A���������ׂ��@�\㉚�G�̏�����㉛�����⑦���͖����܂��ł����A�ǎ҂̓{�肪�a�l�Ɍ�������Ƃ����Ӗ��ł́A���͍I���Ɍ��͎҂։�����Ă���Ƃ������܂��B��i�́A�ǎ҂�������������̂Ȃ̂�������܂���B |
|
|
|
�����ǂ��B ���R����u���`���`�̖v
�m�[�x���܍�Ƃł����[�N���̑�\��u�ɓ��̗x�q�v�ɁA�u���ȂÂ����̂͒N���v�Ƃ�����肪����܂��B����̏I�ՂŊw���́u���v���D�ɏ���ėx�q�ƕʂ���ʂŋN������ł��B ��i�ɂ́A�y�x�q�͂�͂�O�����ƕ����܂܈�������߂Ă�B�������q�ɑ��܂낤�Ƃ��ĐU��Ԃ����A���悤�Ȃ���������Ƃ������A������~���āA����������ȂÂ��Č������B�z�Ə�����Ă��܂����A�u���ȂÂ��Č������v�̎��͒N���Ƃ������₪�A�ǎ҂����[�̌��ւ��т��ъ�ꂽ�����ł��B��[�́A������O�̉ӏ��ŗx�q�����ȂÂ��Ă���̂�����A�u�������v�Ə����Ă���ȏ�A�����ł��ȂÂ����̂͗x�q�Ɍ��܂��Ă���ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂����B�Ƃ��낪�A��l�̓ǎ҂Ƃ��ēǂݕԂ������A��̈ꕶ���u���v�Ŏn�܂邽�߁A�u���悤�Ȃ���������Ƃ����v�̂��u���ȂÂ��Č������v�̂��u���v�Ƃ���̂��A�����Ȃ��Ƃł͂Ȃ��ƍl�������߂��̂ł��B �@�@�s�Ԃ�ǂ߂A���͗x�q�ł���A�u���v�ł͂Ȃ��ƌ����邩������܂��A�u���悤�Ȃ���������Ƃ����v�̑O�Ɂu�x�q�́v�Ƃ�����ꂪ�Ȃ����߁A��ǂ����܂�₷���Ȃ��Ă���̂ł��B��������[�́A�����łł������Ɏ���₤���Ƃ��ł��܂���ł����B�Ȃ��Ȃ�A����Ă��܂��ƍ��x�́A�u����̌���͉��ҁv�Ƃ�����肪�������Ă��܂�����ł��B����͂�������l���́u���v�Ȃ̂ł����A���́u���v�́A�x�q�ɂ���������͂��̂Ȃ��u���悤�Ȃ���������Ƃ����v�Ƃ����S������Ă��܂�������A�I�悵�Ă��܂��̂ł��B ���O���ꋳ�ȏ��ɂ���֓������́u���`���`�̖v�́A���|���鏭�N���A�a�C�œ|�ꂽ�c���̂��߂ɁA�铹�������Ĉ�҂��Ă�ŗ���Ƃ�������ł��B�E�C�Ɛ����̂��b���ł����A��肩����l�Ȃ��̕��̂̎�A���肪�N�Ȃ̂��Ƃ����_�ŕ����̉��߂��\�ɂȂ��i�ł�����܂��B������Ɍ�肩����l�ȕ��̂́A��l�������̎��_�Ɋ��Y���Ă��܂����A���Ƃ��Ă̓������O�l�̂Ƒ����ēǂޑ��ɁA�����̂��Ƃ��u�����v�ƌĂԏ��N�̈�l�̂Ƃ��ēǂނ��Ƃ��ł���̂ł��B �@�@���炩���ߔz�������߂Ă��̍�i�����ǂ��Ă݂�Ƃ悭������܂��B�O�l�̓o��l���A�����A�����܁A��җl�ƁA�n�̕��̌����ʁX�̐l�ɓǂ܂���ꍇ�ƁA������Ɠ����q���̐��œǂ܂���ꍇ�Ƃł́A��i�̈�ۂƓ��e�������A�ς���Ă���͂��ł��B �@�@��i�̌����́A�ǎ҂̓ǂ݂ɂ���ĕω�����Ƃ������ƂɂȂ�悤�ł��B |
|
|
|
�����ǂ��C ��4����u���ˁv
�u����A���O�������̂��B�����I�����ꂽ�̂́B�v����́A��������Ɩڂ��Ԃ����܂܁A���Ȃ����܂����B���\�́A�Γ�e������ƁA�Ƃ藎�Ƃ��܂����B�������A�܂���������ׂ��o�Ă��܂����B ���S���ꋳ�ȏ��Ɍf�ڂ���Ă���u���ˁv�́A�{���ƕ��я̂���银�b��Ƃ̐V����g���P�W�̎��ɏ������A���{���\���鍑���I���b�ł��B����͓�g���c���̍��ɕ������ꂽ���`�����Ƃɑn�삵�����̂ł����A�����G���u�Ԃ����v�Ɍf�ڂ����ۂɔ��s�l�̗�؎O�d�g�̓Y����Ă���A�O�q�̌����ȏ��œǂ܂�Ă��錋�������̓Y��o�[�W�����ł��B ���̕���̋��ȏ��ւ̗̍p���́A�P�X�V�O�N��ȑO�͂R�����x�ł������A�V�O�N��ɂV���A�W�O�N��ȍ~�͑S�Ă̋��ȏ��Ɍf�ڂ���鍑�����ނƂȂ�܂����B�V�O�N��܂ł̓lj��w���́A�����҂̎����߂����ݍӂ��Đ��k�ɓ`�B����ÓT�lj��^�̂��̂ł������A�p�^�[���������lj��w�����q�ǂ��̍��ꌙ�����������Ƃ������Ȃɂ��A�W�O�N��ȍ~�́A�ǎ҂́u�ǂ݁v�̑��l���d�����e���_�^�̎w�����s����悤�ɂȂ��Ă����܂��B�u���ˁv�̉��߂��A�����}���̋��t�p�w�����́A�S���ƕ��\���S���́u���������Ēʂ����������Ɓv���������Ă���̂ɑ��A�������Ђ̂���́A�u����ʂ��Ă����������������Ƃ��ł��Ȃ������߂����v����������Ƃ����悤�ɁA���ȏ���Ђɂ���ĈႢ�������Ă��܂��B �ʂ����āu���ˁv�́A�Ō�ɂ͗������������Ƃ��ł����n�b�s�[�G���h�̕���Ȃ̂ł��傤���B����Ƃ����ɂ���Ă����C�����𗝉�����邱�Ƃ̂Ȃ������ߌ��Ȃ̂ł��傤���B����͂܂��ɓǂݎ�̎��R�ȁu�ǂ݁v�ɋA���邱�ƂȂ̂ł��傤�B���̕����ǂ��k�̒��ɂ́A�S�������A�S���ɃE�i�M��D���ĕ�����Ȃ��Ă��܂�����A�S���̗]�v���܍ߍs�ׂł��킵�����瓐�l��������Ђǂ��ڂɑ��������\�ɓ���A�u�S���͌�����ē��R�������v�Ƃ��������������q�����܂��B������܂��^���̈��������܂���B�����^���ƐM���邩�A����^���Ƃ��đI�ю�邩�́A�ǎ҂̎��R�Ȃ킯�ł��B �Ƃ���ŁA�P�W�̐V����g�����������e�̌����́A��؎O�d�g�̓Y��o�[�W�����ƈꕔ�قȂ�A���\�̎��_����S���̎��_�Ɍ�肪�ڂ��Ă��܂����B �u����A���O�������̂��B�����I�����ꂽ�̂́B�v����́A��������Ȃ����܂܁A���ꂵ���Ȃ�܂����B |
|
|
|
�����ǂ��D ���T����u�呢��������ƃK���v �@ �l�Ԃ̔����ɂ́A���q�I�Ȕ����ƁA�s�א��s�I�Ȕ���������܂��B�u�����Ɋ�������v�Ƃ����̂́A��̎����̏��q�ł����A�u�����̊��A�������Ƃ��āI�v�Ƃ����̂́A�N���ɖ������藊�肷���̍s�ׂł��B���q�͂��̓��e�ɂ��Đ^�U���m��ł��܂����A�s�ׂɂ͐^���U������܂���B������������I�ɍs�������̑啔���͌�҂ł��B�����Č�҂ɂ͕K���A���̔������s�ׂƂ��Đ��������鑶�݂ł��鑼�҂����܂��B �����̏o�镨��ɂ́A���Ƃ��b��t�@���^�W�[�Ȃǐl�ԂƓ��l�ɍl������b�����肷��L�����N�^�[���o�ꂷ��b�ƁA�l�Ԃ̖ڂŊώ@���������̎p��`�������I�Șb������܂����A�u���ˁv�ȂǑO�҂́A���q���Ƃ��Ă͊��S�Ɂu�U�v���ƌ�����ł��傤�B����A�u�V�[�g�������L�v�Ȃnj�҂́A�u�^�v�ł��邱�Ƃ��O��ɂȂ��Ă��܂��B �����\�̏������u�呢��������ƃK���v�͌�҂̃^�C�v�̕���ł����A�^�U��₤�Ɓu�U�v�ł��낤�Ǝv���镔�����������܂��B��l�̎�l�ƁA�n�蒹�̃K���̓��̂Ƃ̒m�b��ׂ�`�����̕���́A���̐ݒ�ɂ����Č�肪�w�E����Ă��܂��B�܂��A����ƂȂ鎭�������̌I��x�ɂ̓K�����Ȃ̌Q�ꂪ�n���Ă����L�^�͂Ȃ��A�n���Ă��Ă����̂̓J�����Ȃł����B�呢��������̑���̓K���ł͂Ȃ��J���������悤�ł��B�܂��A�呢�������߂܂����K�����ނɂȂ��A���̌���ɂƂ܂�悤�ɂȂ����Ƃ����`�ʂ�����܂����A�K�����J�����l�̌���͂߂�悤�ȋr�͎����Ă��܂���B ���̖̂ʂł��������ȏ�������܂��B����͕M�҂Ɍ�����呢��������̎��_�Ői�s���Ă��܂����A��������̎d�|�������̃K�����n���u�T�ɏP��ꂽ���́A�u�c��̖ڂɂ́A�l�Ԃ��n���u�T������܂���ł����B�����A�~��˂Ȃ�Ȃ��Ȃ��܂̂����������邾���ł����B�v�Əq�ׂ��A������͂��̂Ȃ��K���̃��[�_�[�c��̐S��`�ʂɂȂ��Ă��܂��B����́u�U�v�ł��傤���B �u���[���B�K���̉p�Y��B���܂��݂����Ȃ���Ԃ��A����́A�Ђ��傤�Ȃ�肩���ł�����������Ȃ����B�v�n���u�T�Ƃ̐퓬�ŏ������̂̉�҂��āA�t�̒��A�呢��������͎c�����ɕ����Ă��܂��B�킢��ʂ��Ċ��Ɏc��͑呢��������̑��҂ƂȂ��Ă��܂������A���̌�肩���ɂ���Ă��̑��Ґ��͊m�łƂ������̂ɂȂ�܂��B����܂��āA�M�ҁA�ǎ҂Ƃ������҂Ɍ���镨��̑S�̂��A��̍s�א��s���Ɖ��߂���A�^���U������܂���B |
|
|
|
�����ǂ��E ���U����u��܂Ȃ��v
�u�N�����{���͂�������B�v �u�N�����{���͂��Ղ��Ղ�������B�v ���ď����͐��ɏo���ēǂނ��̂ł���A����Ƃ͕����ʂ�u���v���u���v���Ƃł����B���ꂪ�ߑ�ɂȂ�Z���ԂŊw�K�E�����W���邽�߂̓Ǐ�����ʉ��������ƂŁA�Ǐ��͂ӂ��ٓǂōs�����̂ɂȂ�܂����B�Ƃ���ŁA���ɏo���ēǂނ��Ƃ����ǁA�܂��͘N�ǂƌ����܂��B���ǂ͕����������ɕϊ����邱�Ƃ��Ƃ��āA�N�ǂƂ͉��ł��傤�B �w�Ԃ��Č��x�Ƃ������悪����܂��B�ЎR���L�I�E��A���S���E���āA�e�[�}�͘N�ǂł��B�Љ�l��N�ڂ̏������A�Ђ��Ȃ��Ƃ���N�ǂ̍˔\�����o����A���̖��͂ɖڊo�߂Ă����Ƃ����ِF�X�g�[���[�̑�ꊪ�ŁA��l���͂������������̏����̂��߂ɘN�ǂ��邱�ƂɂȂ�܂��B���̍ۂɓǂ܂ꂽ��i���A���Z���ꋳ�ȏ��ɂ��f�ڂ���Ă���{���́u��܂Ȃ��v�ł��B �w��܂Ȃ��x�́A�J��̒�̊I�̌Z�킪�ڂɂ��������������̐��E��`������i�ł��B�{���ɂ́A��ǂ�����ɓǎ҂��A�u�ŁA�����牽�E�E�E�v�ƌ��������Ȃ��i���悭����܂��B�N���]���̂͂����肵�����̍�Ƃ̎������w�ɔ�ׁA���̂悭������Ȃ��A�s�v�c�ȕ��ꂪ�����̂ł��B�u��܂Ȃ��v���A��҂̈Ӑ}������肪�����ɂ�����i�ŁA�u���Ղ��Ձv��炤�u�N�����{���v�Ȃ鐳�̕s���̑��݂��o�ꂵ�A��������A�E���ꂽ�肵�܂��B ���̑����ǂ���̂Ȃ���i���A�u�Ԃ��Č��v�̎�l���ɂ���ĘN�ǂ���鎞�A����Ƃ͘N�ǂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł��邱�Ƃ��A�ɐɗ�������܂��B��l���́A�w��܂Ȃ��x�`���́u�N�����{���͂�������B�v�Ƃ����Z���t���I�Z��̌Z�A�u�N�����{���͂��Ղ��Ղ�������B�v���̐����œǂ݂܂��B�X�ɁA�P������̔ނ�̎��_�Œn�̕���ǂ݁A���[�R�O�����̐����A�l�ԂȂ�R�O���Ɍ�����[���������E�Ƃ��čČ����܂��B�����āA���́u�ǂ݁v�̍���������ƓK�i�ɉ��A�u�N�����{���v�Ƃ͉����ɂ��������o���܂��B�@ �u��s����Ƃ��Ӗ���������Ȃ���ΘN�ǂ͂ł��Ȃ��B�v���̖���͂����`���܂��B����́A�������N�ǂ��ł���悤�ɂȂ������ɂ́A���ɖ{���̓lj��͒B������Ă���Ƃ������Ƃ��Ӗ����܂��B�������A���߂͈�ł͂���܂���B�ł����琳�����lj��Ƃ́A��i�ʂƂ��Ă��̕��ꐢ�E���Č�����A�����̐��̗D�ꂽ�N�ǂ̂��Ƃ��ƌ�����̂�������܂���B |
|
|
|
�����ǂ��F ���P����u���N�̓��̎v���o�v
���|��]�́A�u�s�����Ȕ�]�v�Ɓu�����Ȕ�]�v�ɕ��ނ���܂��B�u�s�����Ȕ�]�v�Ƃ����̂́A�ΏۂƂ����i������I�ȍ\�z���Ƃ��đ����A���̌`����̎d�g�݂���i�̊O�����番�͂�����@�ł��B���āu�����Ȕ�]�v�́A��i���E�Ɠǎ҂̐��E�Ƃ̊Ԃ̎d�������āA��i�̒��ɓ��荞��Ř_����悤�ȕ��@�ł��B�O�҂́A��i�ɕ`���ꂽ�q�ϓI������������]�̑Ώۂł����A��҂ł͍�i�ɕ`����Ă��Ȃ����ƁA�Ⴆ�u�����Y�̋o�c�q���s����������A���Ɖ���賂͋S�ގ�����`���Ă��ꂽ���H�v�Ƃ��������ݒ�𗧂Ă��肵�܂��B �u�����Ȕ�]�v�͍�i����̈�E�Ƃ��Č�����ʂ�����܂����A���R�ȑz���͕����ǂފy���݂̈�ł�����܂��B�܂��A�u������������l���Ȃ�v�Ƃ�������́A�����̎��Ԃ�Ǐ����z���ɂ͌������Ȃ��퓅��ł��B ���ꍑ�ꋳ�ȏ��ɂ́A�m�[�x���܍�ƃw���}���E�w�b�Z�́u���N�̓��̎v���o�v�Ƃ����������A�U�O�N�ȏ���̊ԁA�f�ڂ��ꑱ���Ă��܂��B���{�ł͗L���Ȃ̂ɁA�{���h�C�c�ł͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��Ƃ��������ς������i�ł��B ����́A�u���v�̉ƂɖK�ꂽ�q�́u�l�v���A�u���v�̒��̕W�{�����āA���̍̏W�ɖ������������N�̓��ɔƂ����o���������Ƃ������̂ł��B���N�̓��́u�l�v�́A�G�[�~�[���Ƃ����q������������̕W�{�𓐂�ɏ����Ă��܂��܂��B�G�[�~�[���Ɏӂ�ɍs���̂ł����A�y�̖̂ڂŗ₽���������ꂽ�u�l�v�́A�u��x�N�������Ƃ́A���������̂ł��Ȃ����̂��v�ƌ��A�����̏W�߂�����S�ĉ����Ԃ��̂ł����B ���̍�i�ɂ��āA�����������u�l�v��������Ƃ������z���q�����A�u�l�v�̐S���G�[�~�[���̌����ɂ��āA�݂��ɋ���������A���������肵�Ȃ���A�����I�ȋc�_�����邱�Ƃɂ́A�������Ӌ`������܂��B�u�����Ȕ�]�v�B �������A����x�u�s�����Ȕ�]�v�ɖ߂�A��i�̋q�ϓI�ȍ\���ɖڂ������Ă݂܂��B���̕���͈ꌩ�A�u�l�v���u���v�Ɍ�����b�Ƃ����\���Ɍ����܂��B�ł��A���ۂɂ��̕����ǎ҂Ɍ���Ă���̂́u���v�ł��B�����āA���̓ǎ҂̒��ɂ́u�l�v���܂܂꓾��̂ł��B�ꂢ���N�̓��̎v���o���O�҂ł���u���v�Ɍ�蒼����邱�ƂŁA���̈Â��v���o�͋q�ω��E���Ή�����A�l�̒��̓{�����J��߈������A�悤�₭�X�����Ă����̂ł��B�u�l�v�ƈ�̂ƂȂ����ǎ҂��u�l�v�̗���ɗ����Ă��̋C�����𗝉����悤�Ƃ����ϓI�ȁu�����Ȕ�]�v�̑��݂��A�u�l�v�̗���������ɔ�]�ł���q�ϓI�ȍ\���̒��ŁA�����ۏ��Ă��܂��B |
|
|
|
�����ǂ��G ��2����u���ꃁ���X�v
���͂������ɂ͓��@���K�v�ł��B����́A������`����������ł���A�N���ɓ`���������炩�̎v���ł��B�앶�������Ȃ��q���앶�������Ȃ��ő�̗��R�́A���̓��@�������Ă��邱�Ƃɂ���܂����A������A��Ƃɂ͏����ׂ����@�A�܂�A�z�肷��ǎ҂�A���̓ǎ҂ɓ`�������������K�v�ł��B ���ꋳ�ȏ��Ɍf�ڂ���Ă���u���ꃁ���X�v�́A�F���M���̑�����`�����i�Ƃ��čL���m���Ă��܂��B�A�j����i�ɂȂ�����A�����ɂȂ�����A�p���f�B�����ꂽ��A�����ǂ�ł��Ȃ��Ƃ����e�͒m���Ă���Ƃ����l�͏��Ȃ�����܂���B�������̋������e����A����̏�Ŏg�p����邱�Ƃ�������i�ł����A�u�l�Ԏ��i�v�Ȃǂ̍�i�Œm�����҂̑��Ɏ��́A�s�ς�S���̏�K�ƂŁA���܂蓹���I�Ƃ͌����Ȃ��G�s�\�[�h��L�x�Ɏ����ƂŗL���ł��B �u���ꃁ���X�v�̓h�C�c�̕����V���[�̎��u�l���v������Ƃ��Ă��܂��B�\�N�f�B�I�j���\�X�̎E�Q�����݂������X�͕ߔ�����A���Y��鍐�������̂́A���̍�����ς܂��ċA���Ă���܂ŌY�̎��s��҂悤�ɗ��݁A�e�F��l���Ƃ��č����o���B�O����A�����������̐�A�����̏P���A�Ă������z�Ȃǂ̏�Q����蔲���A���Y���s���O�A�e�F�̑O�Ɍ���郁���X�B�S�ł��ꂽ�����͔ނƗF�������A���S����B�u�l���v�̓��e�́u���ꃁ���X�v�Ƃقړ����ŁA�����X�͓����I�ȃq�[���[�ł��B�ł��A���ɂ�������������@�ƂȂ����o�����́A���܂蓹���I�Ƃ͌����܂���B ���鎞�A�M�C�̗��قő��ɂ́A�F�l�ō�Ƃ̒h��Y�ƈꏏ�ɐ������ݕ����A��l�͋����g���ʂ����Ďx�����s�\�ɂȂ�܂��B�����ŁA���ɂ͒h��l���Ƃ��ďh�Ɏc���A�����֎؋��ɍs���܂��B�������A�����҂��Ă��ނ͖߂�܂���B���т��炵���h�́A�x������҂��Ă��炢�A�����֍s���Ă݂�ƁA�ނ͉��t�̈䕚����̉Ƃł̂ɏ�����ł��Ă��܂����B���{����h�ɑ��ɂ́A�u�҂g���h�����ˁB�҂�����g���h�����ˁB�v�ƙꂢ�������ł��B �u���ꃁ���X�v�Ɓu�l���v���ׂ�ƁA�O�҂ɂ́A�F�̐M������낤�Ƃ��鎩���ɐ����s���i���V�X�g�ȓƔ���A�����O�ɂ��Ă��錾���ڗ����܂��B�����I���߂́A���`���т��҂���ǂɒ��ʂ����ۂɌ����銋���Ƃ��Ă����������܂��B�������A�h�𗠐������Ɏ��ɂƂ��Ă��̍�i�́A���̈������L���@���A�����Ȑl�ԂƂ��ẴA�C�f���e�B�e�B����邽�߁A�V���[�̎��ɑ����Ă����炦���A�������g�ւ̌��������̂�������܂���B |
|
|
|
�����ǂ��H ��3����u�̋��v
�u�ӂƂӂ��Ƃv�Ƃ����_�W�������O����ɖ|�邱�Ƃ͉\�ł��傤���B�P��ɕ������Ē����ƁA�u�ӂƂ�v�Ɓu�ӂ��Ƃ�v�̔����̗ގ����͏����Ă��܂��܂��B�����������t�V�т�A�Z�́E�o��Ȃǂ̒�^���̃��Y���������ɖ|�邱�Ƃ͓�����ł��B�ƂȂ�ƁA�|��҂������̓`���悤�Ƃ��邱�Ƃ����S�ɓ`���邱�Ƃ͕s�\���ƌ��������ł��B ���R���ꋳ�ȏ��Ɍf�ڂ���Ă���u�̋��v�́A�����̕����ł���D�v�̑�\��ŁA���g�̑̌�����ɂ����Ƃ�����i�ł��B�n�傾������l���̎��Ƃ͖v�����A��ƂŌ̋��̉Ƃ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B�]���̏����̂��߁A��l���͂Q�O�N�Ԃ�Ɍ̋��A��A�����ŏ��N����̗F�l�œ���̑��݂����������g�E�ɏo��܂����A�ނ͎�l�����u�U�ߗl�v�ƌĂсA��l�̊Ԃɔ߂����g���̍������邱�Ƃ���l���͓˂��t������̂ł��B�������A�ނ̉��������g�E�̑��q�Ɛe�����Ȃ�A�ĉ����Ă������Ƃ�����l���́A�Ⴂ����̊�]���関�����肤�̂ł����B ���ȏ��Ɍf�ڂ���Ă���u�̋��v�̖|��͒������w�҂̒|���D���s���Ă��܂��B�������A���ɂ��\�l�ȏオ�|�A���̓��e�͗v���v���ł��Ȃ��ۂ̈قȂ���{��ɂȂ��Ă��܂��B�|��҂̐��������߂̈قȂ�u�̋��v�����܂�Ă���킯�ł��B �̋��𗣂��D��ʼn��̃z�������u�l�����A���A���Ă���́v�Ǝ�l���ɕ����V�[��������܂��B�ނ̓����g�E�̎q�V���C�V�����ƗV�Ԗ����Ă����̂ł��B�������l���Ƃ��̕�́A�u�͂��Ƌ������ꂽ�v�ƒ|���͖Ă��܂��B�������������������t�v�́u��Ǝ��͂���ɋC������āv�ƖA���g�~�́u�킽�����ǂ��͔��琇���Ȃ��Ă����v�A���c�́u�Ȃ�ƂȂ�����߂����C�����ł������v�ƖĂ��܂��B����A�D�v�̌����́u��a��e��s�L�����R�v�ƂȂ��Ă��܂��B�u���R�v�Ƃ́u�����������āA�������肵�A�������Ȃ��l�q�v��\�����t�ŁA�q�����������킵���ʂ����ꂪ�������A�Ȃ��C�����ɂȂ��Ă��܂�����l�������̕��G�ȗl�q��\�����Ă���̂ł��B �|��Ƃ́A�P�ꃌ�x���Ō����͂��A�����ڕW����ōō\���������Ƃł����A����͌����̍Đ���ڎw���čs����Q���n��ł��B����̑�͕ς��Ȃ��Ă��A�ו��̕\���͖|��҂̑n���͂Ɉς˂��Ă���̂ł��B |
|
|
|
�����ǂ��I ���Z����u�R���L�v
�u�l�Ԃ͂���ł��ҏb�g���ł���A���̖ҏb�ɂ�����̂��A�e�l�̐���Ƃ����B����̏ꍇ�A���̑����㵒p�S���ҏb�������B�Ղ������̂��B�v ������f��ł��A�l���l�Ȃ炴��ٗނɕω����镨�ꂪ�悭����܂��B�T��ւ��墂�S�L�u���A�l�͐F��ȕ��ɕϐg���Ă��܂��悤�ł��B���{�̔\�ł́A�������݂̔O����S�ƂȂ�b����̌^�ɂȂ��Ă��܂����A�S�̈ŁA���̐���A�����̒��ɐ��ޖҏb��}���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ������A���g���O�����ҏb�ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B ���Z�̍��ꋳ�ȏ��Ɍf�ڂ���Ă��钆���ւ́w�R���L�x�́A����ȕϐg杂̈�ł��B���̎���̒����A�Ⴍ���ĉȋ������ɍ��i�����G�˂̗����́A�G���[�g�R�[�X�ɂ���Ȃ���A���̖�l�Ƃ��đ����ȏ�i�ɋ�������A���l�Ƃ��Ă̖����悤�ƁA���E��ނ��܂��B�������A�����͗g���炸�A�������ꂵ���Ȃ�A�Ȏq��{�����߂ɉ�����l�Ƃ��čĂѓ������ƂɂȂ�̂ł����A���̋����ɔނ̃v���C�h�͏����A���ɔ������Ď��H���Ă��܂��܂��B������A�o�����������̋��F���A�����ŕ����������A��g���ɍs�������A��C���֖҂ȌՂɏP���܂��B���͂��̌Ղ����A�������������̕ς��ʂĂ��p�ł���A���肪���F�ł��邱�ƂɋC�t���ƁA��炢�����Ƃ���߁A�₪�ĒႢ���Ŏ������ՂɂȂ����o�܂����n�߂�̂ł��B �u���a�Ȏ����S�ƁA�����㵒p�S�v���ꂪ�������Ղɂ��������A���邢�͌Ȃ̒��̖ҏb�������Ɨ����͍������܂��B�u���}�̋S�ˁv�ƌĂ�A���ɂ���Ė��𐬂����Ƃ�������������Ȃ���A�����̖��˂��ӎ��������Ȃ������߂ɁA�t�̎w�����邱�Ƃ�A�L�\�Ȏ҂Ƌ����������Ƃ������u���a�Ȏ����S�v�B�������\�̗͂��҂̉��œ�������A�ނ�ƌ�������肷�邱�Ƃ�p����u�����㵒p�S�v�B���ꂪ�ނ𐢊Ԃ��牓�����A�����̊k�Ɉ��������点���u�Ձv�������̂ł����B �u�l�Ԃ͒N�ł��ҏb�g���ł���A���̖ҏb�ɓ�����̂��A�e�l�̐���v�Ɨ����͌����܂��B�����⎹�i�A���~�∤�~�A�l�X�Ȑ���ɂ��l�X�Ȏ����S�Ɏx�z����A�l�i��Q�Ɋׂ�A���l��ƍߎ҂ɕω����Ă��܂����Ƃ��A�������͖��ӎ��ɕ|��Ă��܂����A�u���R�����炸�ɉ����t����ꂽ���̂��l���������āA���R�����炸�ɐ����čs���̂��A��X�������̂������߂��v�Ƃ��A��҂͏����Ă��܂��B�ԂȂ�ʎ����Ƃ����ҏb�����B��j��̂��A����͗\���s�\�Ȏ���������܂���B |
|
|
|
�����ǂ��J ���Z����u������v
���B�́A�Љ�̒��Ŏ���������ׂ��ʒu�≉����ׂ������������ƁA���_�I�ɕs����ɂȂ�A���炩�̐_�o�����Ɋׂ�댯������܂��B���̂��߁A���݂̈ʒu�E�������m�肷�镨��Ƃ��Ď��ȓ��ꐫ�E�A�C�f���e�B�e�B�����A���ꂪ��Ȃ��悤�Ɏ����S�E�v���C�h�Ƃ�������ŃK�[�h���Ă��܂��B���������_�o�V�X�e���ɂƂ��đ厖�Ȃ̂́A�P�l�Ƃ��Ă̕���∫�l�Ƃ��Ă̕���Ƃ��������ȓ��ꐫ�̒��g�����A���������Ă���v���C�h�������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃł��B �H�열�V��́w������x�ɓo�ꂷ�鉺�l�́A�d���Ă�����l����ɂ��o���ꂽ���ƒ��̎�҂ł��B����́A���̉��l�������Ă������߂ɓ��l�ɂȂ�ׂ����ۂ��A�I���𔗂��Ă������n�܂�܂��B�ނ͌��f�ł��ʂ܂܁A�r��ʂĂāA���̂̎̂ď�ƂȂ��Ă����������̗�����ŁA�ЂƂ܂����𖾂������Ƃ���̂ł����A�����ŏ��̎��̂̓����獕�������������Ă���V�k��ڌ����܂��B�V�k�̍s�ׂ��������������s�ƌ����ނ́A���`���ɋ���āA���������Ĕޏ��ɔ�ъ|����A��艟�����܂��B�������A������Ă������̂̏����A���O�͊������ƌ����Ďւ̓����Ă������߁A�����邽�߂ɔޏ��̔����ăJ�c���ɂ��悤�Ƃ��鎩���������Ă���邾�낤�ƌ����V�k�̘b���ƁA��]���ē��l�ɂȂ�E�C�����炢�A�V�k�̒������͂�����āA���苎���čs���̂ł����B ���̏����́A�l�Ԃ����G�S�C�Y���̌�����\���������̂Ƃ��Č���܂����A���̖ʔ����́A�l�Ԃ̃A�C�f���e�B�e�B�ɂ͐ߑ��������Ƃ����e�[�}�ł��B ���B������s��������ہA�����Ă��̍s���̏�Q�ɂȂ�悤�Ȏ������āA���s�������̌�����Ƃ���s�ׂ��A�Z���t�E�n���f�B�L���b�s���O�ƌ����܂��B�v���C�h�������Ȃ����߂̐_�o��p�ł��B���l�͗�����̉��ŁA���l�A�C�f���e�B�e�B�I���̌��f�𔗂��Ă��܂����B����Ȏ��A�X���V�k���X�����Ƃ����Č����Ă��ꂽ���߁A�ނ͂������艟������Ƃ����i�D�̃Z���t�E�n���f�B�L���b�s���O�����{���܂��B�����ɂ͐��`��������A�Ƃ������Ƃň��l�Ƃ��Ď��s���Ă��ނ̃v���C�h�͎���܂��B����A�V�k�̘b���āA���݂����Ă��������Ɏ����͂���̂��ƁA�P�l�Ƃ��Ď��s���邽�߂̌���������Ă��܂��B ���l�ɂȂ������Ɍ����܂����A���ۂɂ́A���̌�̔ނ��P���ǂ���̎��ȓ��ꐫ�ɗ����������s���ƌ�����ł��傤�B �u���l�̍s���́A�N���m��Ȃ��B�v |
|
|
|
�����ǂ��K ���Z����u������v
���Z�̍���̋��ȏ��Ɍf�ڂ���Ă���ߑ㏬���̒��ōł��L���ȍ�i�Ƃ����A�Ėڟ��́w������x�ł��傤�B�C�O�̑�w�Łw��������Ɂx�����ň�������{�̍�i�ł���A���w�̐��E�ɂ����ē��{�̊�ƂȂ��Ă��܂��B���Ƃ��Ƃ́A�����w������x�Ƃ����Z�ҏW�̈�Ƃ��ď������Ƃ�����i�ł������A�����Ȃ肷�������߁A���̈�҂������o�ł��ꂽ�̂ł����B ��i�́u�搶�Ǝ��v�A�u���e�Ǝ��v�A�u�搶�ƈ⏑�v�Ƃ����O���\���ɂȂ��Ă��܂��B���߂́u�搶�Ǝ��v�ł́A������吶�́u���v���A�C������ŋ��R�o������j���ɋ�����������A�ނ��u�搶�v�ƌĂ�Ō𗬂��Ă����l�q���`����܂��B�u�搶�v�́A������u������v�����Ȃ�����������A�e�̎��Y�����Ő������鍂���V���ł��B��呲�Łu���v�Ɛ�U���߂��A�[���w���ƌ����������Ă������߁A�u���v�͑�w�̋������������u�搶�v�̕��Ɍh�ӂ�����悤�ɂȂ�܂��B����ȁu�搶�v�ɂ́A�ߋ��Ɋւ��邠��閧������܂��B���ꂪ�ނ��Љ��u�Ă錴���������̂ł����A���̔閧�ɂ��Ă͌����Č�낤�Ƃ��܂���ł����B�����A�u�i���̒��́A�P�l���j�}�Ɉ��l�ɕς���狰�낵���̂ł��v�A�u���͍߈��ł���v�Ȃǂ̌��t���u���v�ɕ������邾���ł����B ��ڂ́u���e�Ǝ��v�́A��w���ƌ�̉ĂɁu���v���A�����A���e�Ǝ��Ƃʼn߂������킪�`����܂��B�����q�������āu���v�̑��Əj�������悤�Ə������Ă���ƁA�����V�c��Ă̐V��������A���˂Đt����a��ł��������A����ɂ���悤�ɑ̒������������A�I�ɂ͖����ɗՂސg�ƂȂ�܂��B���̕��̊ŕa�����Ă����u���v�̂��ƂɁu�搶�v����̕������莆���͂��܂��B�u�搶�v�̈⏑�ł����B �Ō�́u�搶�ƈ⏑�v�ɂ́A�u�搶�v���Љ��u�₳���A���̍˔\�����悤�ƕ��N����x�ɁA�u���O�͉������鎑�i���Ȃ��j���v�ƌ����Ĕނ̑��������A�ނ̐S�������s�v�c�ȗ͂����܂ꂽ�o�܂��`����Ă��܂����B�⏑�ɏ����ꂽ���ƗF��Ǝ��i�Ɨ���A�����Ď��B �u�L�����ĉ������B���͂���ȕ��ɂ��Đ����ė����̂ł��B�v �u�搶�v�́A�@�����Ƃ̂ł��ʎ��҂ւ̌��߂�����w�����A�����ׂ����Ƃ��ł��ʂ܂܁A���E���̂悤�ɂ��ď\���N�̍Ό����܂����B�����āu���R�ƓƗ��ƌȂ�Ƃɏ[��������ɐ��ꂽ��X�́A���̋]���Ƃ��Ă݂�Ȃ��̗҂��݂𖡂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�v�ƌ����A��������̏I���ɏ}���Ď��ʂ̂ł����B �ߋ��Ɍ��߂��������l�Ԃ̐S��f�߂���A���҂Ƃ��Ă̎��ҁB�G�S�C�Y���Ɨϗ��́A�����̋��J�Ɋׂ����҂ɂ̂�����H��B�����w������x�́A���������������E�Ɏ��݂���S��́A���A���e�B��`������i�Ȃ̂�������܂���B |
|
|