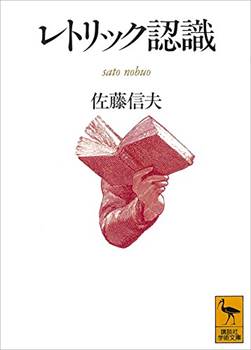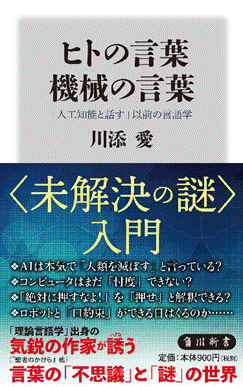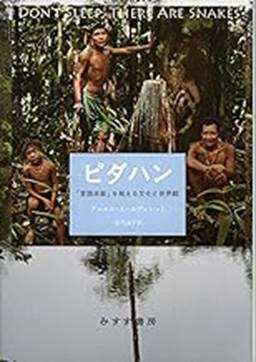|
�@�Q�O�Q�R�N�x���ʃR���� �u���t�ƐS�Ɛ��E�v |
|
|
|
�@ �@ �@�@�u���t�̔��B�̓�������v�@����ނݒ� ���� �q�Ԃ����̕��K���r �@ ���Ȃ����ǂ������t�̕�����Ȃ��O���̎R�֍s�����Ƃ��܂��B���n�̐l���K�C�h�����Ă����̂ł����A���̌��t�͑S��������܂���B����U�Ă�����A�E�T�M����ђ��˂Ă��܂����B�K�C�h�̐l��������w�����āu�K���@�K�C�v�ƌĂт܂����B���āA�u�K���@�K�C�v�Ƃ͉��ł��傤�B���Ȃ��͂܂��A�u�E�T�M�v�̂��Ƃ��낤�A�Ǝv����������܂���B�ł��A�u�����v�̂��Ƃ�������Ȃ����A�Ƃ��v���A�u���v�̂��Ƃ��ȁA�u��ђ��˂邱�Ɓv��������Ȃ��A�Ƃ��v���Ă��āA�l���Ă��邤���ɉ����u�K���@�K�C�v�Ȃ̂�������Ȃ��Ȃ�܂��B ����́A�N�w�҃N���C���̒����u�K���@�K�C���v�Ƃ������̂ŁA���錾�ꂪ�w������Ώۂ����Ȃ̂��A�ʂ̌���֖��m�ɖ|�邱�Ƃ��s�\�ł��邱�Ƃ��w�E���Ă��܂��B�O���l�Ɍ��炸�A�Ԃ�������K�����鎞���A��l�ɂƂ��Ă͊ȒP�Ȃ��ƁA�u���ꂪ�p�p�A���ꂪ�}�}�v�Ƃ��������ƂŁA�u�p�p�v��u�}�}�v�����Ȃ̂��A���̊T�O����肷��͓̂�����ƂȂ̂ł��B ���B�S���w�̌����ҁA����ނݎ��͒���̒��ŁA�Ԃ����ɒP�g���C���̂�������̊���o���Ă��炨���Ƃ����Ƒ����A��������̎ʐ^�������āu�p�p�v�Ƌ�������A���̐Ԃ����͎ʐ^�̂��Ƃ��݂�ȁu�p�p�v�ƌ����o��������������Ă��܂��B �������A���䎁�ɂ��ƁA�Ԃ���������炢�ɂȂ�A�u�K���@�K�C���v���y���N���A���āA�V�������t���ǂ�ǂ�o���Ă����悤�ɂȂ邻���ł��B�E�T�M�������āu�K���@�K�C�v�ƌ����Ă��A���ꂱ��畏����邱�ƂȂ����̓����̖��O���Ɨ�������̂ł��B ��̎q�ɁA���O�̒m��Ȃ������̂ʂ�����݂������āu�l�P�v�Ƌ����܂��B�����āA�`���F�������ʂ̂ʂ�����݇@�ƁA�`�͓����ł��F��傫���̈Ⴄ�ʂ�����݇A�A�ʂ̓����̂ʂ�����݇B�A�����ȊO�̂ʂ�����݇C�A�Ƃ����l�̒�����u�l�P�v��I�Ԃ悤�Ɏw������ƁA������Ƈ@�ƇA��I�ю�邻���ł��B�����B�܂őI��ł�����u�l�P�v���u�����v�Ƒ��������ƂɂȂ�܂����A��̎q�͑Ώۂ́u�`�v�ɒ��ڂ��āA�u������ނ̂��́v�Ƃ��đ�����̂ł��B����ɁA�W�F���̂悤�ȕs��`�̕����������āu���`�v�Ƌ����A���̃W�F���ƔS�y�ł��ꂼ�ꓯ���`�̕��̂����A�ǂ������u���`�v�Ɛq�˂�ƁA�W�F���ō�������̂�I�Ԃ悤�ł��B �u�������́v�Ɓu�Ⴄ���́v�����t�ɂ���Ď��ʂ��邱�Ƃ́A�l�Ԃ̕����A�Љ�A�����Đ��E�̊�b�ł���A�Ȋw�I�v�l�̊�{�ł����A��̍����炻�ꂪ�o����͕̂s�v�c�Ȃ��Ƃł��B |
|
|
|
�@ �@ �@�u���{�Ƃ��Ă̏㋉��b�v�@�{��N�풘 ������ �q��l�̏㋉��b�r �F�m�Ȋw�̌����ҁA����ނݎ��́A�����w���t�̔��B�̓�������x�̒��ŁA�Ԃ�����c���������K�����Ă����ߒ����A�u�����v�u�n���v�u�C���v�Ƃ�������ʼn�����Ă��܂��B �u�����v�Ƃ́A�u�`�n�v�Ƃ��u�`�X���v�Ƃ��u�`�_�v�Ƃ������������x���������ƂŁA�����ɂ͋��ʂ��錾�t�̐�ڂ�����Ǝv�����ƁA�����́A��l���w�����āu�~�Y�v�Ƃ��u�E�T�M�v�Ƃ��ĂԂ̂��A�����ȉt�̂⎨�̒����������́A����ȊO�̂��̂ƕ�������̂��Ɓu�v�����ށv���Ƃł��B����́A�u�������́v�Ɓu�����łȂ����́v����[�V�X�e��]�̔����ł�����܂��B�@ �u�n���v�Ƃ́A��������u�|���v�Ƃ��u�K�`���K�`���v�Ƃ��u�R���R���v�Ȃǂ̃I�m�}�g�y���������A������u�`�X���v�ƌ��ѕt���āu�|������v�Ȃǂ̕\����������肵�āA�`���������Ƃ������\�����Ƃł��B�u�傫���Ȃ��v�u���������Ȃ��v�Ƃ������t��m���Ă���q���A�u�D�����Ȃ��v�u���ꂢ���Ȃ��v�Ȃǂƌ�������A�u���Ń{�[���𓊂���v�u���ŐO�ށv�Ƃ����\���������肷��̂͑n���̌��ʂƂ��Đ��܂ꂽ��p�\���ł��B �u�C���v�Ƃ́A�����������ꃋ�[���̌�p���A�V�������t�̔����ƂƂ��ɏC�����A��l�����̃V�X�e���ɋ߂Â��A���t�̈Ӗ���[�߂Ă������Ƃł��B ���������ߒ���ʂ��Ďq�������́A�����ׂ��X�s�[�h�ŕ����K�����Ă����킯�ł����A�w�Z�ɐi�w���A�����Ċo���Ă����Ƃ����i�ɂȂ��Ă���ƁA���t�̏K���͌l�����傫���Ȃ��Ă����܂��B���ɁA���w�E���Z�E��w�ȂǂŊw�Ԋw�p�p��E���p��ƂȂ�ƁA��l�ł��g���邩�ǂ����������Ȃ�܂��B �]�_�Ƃ̋{��N�펁�́A��b�̕n�����ɂ���Đl�����n�����Ȃ�ʂ悤�A�Ⴂ������P�꒠����葱���Ă��������ł��B��������Ē~���Ă�����b�̒��ł��A������\�����u�㋉��b�v�ƌĂсA���̒�����I�蔲�����ܕS�����A�ߒ��u���{�Ƃ��Ă̏㋉��b�v�ɂ����ďЉ�Ă��܂��B ����Ƃ́A���ɑ��݂��鎖�ۂɕt����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�^���������E��l���Z�݂悢���̂֕ς��邽�߂̐ߖڂƂ��āA���ߕ����Ɏg��ꂽ�F�̂悤�Ȃ��̂��Ƌ{�����͌����܂��B�����u�ԁv�����ʂ�ɂ����ʂł��������M���̐F�ʊ��o���L���ł������悤�ɁA��葽���̌�b���g����悤�ɂȂ�A���������l�ŖL���Ȃ��̂ɂȂ�̂ł��B �u�琁v�u����v�u�ۉ�v�u�����v�A�������R�̏o��ɂ��A���낢��ȕ\����������̂ł��B�㋉��b�ɂ߂��荇�����ƂŁA���E�̈Ӗ��͐[�܂�ł��傤�B |
|
|
|
�@ �@ �@�u����w�̋����v�@�����`���A���Ύ��@�� ���O�� �q�F�m����w�r �l�ނ͂��̒a���ȗ������ƁA������������芪�����E�̐X�����ۂɖ��O��t�������邱�ƂŁA���̐��E��c�����Ă��܂����B�������A���������łȂ�������`�e���Ȃǂ̌�b���q���Ă������̃��[���ɔ����邱�ƂŁA��b�̐��ɐ�������Ȃ������̕\�����\�Ƃ���\�͂������A�����̕������o���Ă��܂����B�ł́A�ꏇ���`�A�ڑ����@�Ȃǂ̃��[���s���@�t�́A�ǂ�����Đ��܂�Ă���̂ł��傤�H ����w�҂̐����`�����ƁA�N�w�҂̖��Ύ����ɂ��Βk�`���̒����w����w�̋����x�́A�l�Ԃ̒m�o��L���A����Ȃǂ����@���`�����Ă����ƍl����F�m����w�̗��_���A�N�w�I�l�@�������Ȃ���Љ�Ă��܂��B �u���Y�͉Ԏq�ɖ{��ǂ܂����B�v ���{�ꕶ�@�ł́A���������\�����g���\���ƌ����A�u�ǂ܂����v�̒��ɂ���g���̏������u����v�����̕\���𐬗������Ă��܂��B�������A����w�ł́A �u���Y�������J�����v �Ƃ����\�����g���\���Ƃ��čl�����Ă��܂��B���߂̕��́A�u���Y�v���u�Ԏq�v�ɓ��������āu�ǂށv�Ƃ������ʂ��Ă��܂����A��̕��ł��u���Y�v���u���v�ɓ��������āu�J���v�Ƃ������ʂ��Ă���A�����悤�Ɍ����ƌ��ʂ̊W���\������Ă��邽�߁A�ǂ�����g���\���ƌ��Ȃ����̂ł��B �ł́A�����g���\���Ȃ̂ɁA�Ȃ��O�҂ɂ́u����v���t���A��҂ɂ͂��Ă��Ȃ��̂ł��傤�B�����ɂ́u�������鑤�v�́u�Ԏq�v�Ɓu���v�ɁA��̓I�Ȉӎ����L�邩���������ւ���Ă��܂��B�u���Y�v���������Ƃ��Ă��u�Ԏq�v�̈ӎ���������u�ǂށv�Ƃ������ʂ͐��܂�܂��A�u���v�Ɂu�J�����v�Ƃ����ӎ��������Ă��A�u���Y�v�̈ӎ������Łu�J���v�Ƃ������ʂ͐��܂�܂��B�u�������鑤�v�̈ӎ��̗L�����A���{��̕��@�`�������߂Ă���̂ł��B����ʼnp��́A�u�J����v�u�J���v�A�u�������v�u�����v�A�u�v�u����v�Ƃ����������Ǝ������̃y�A���A���ꂼ��uopen�v�uboil�v�ubreak�v�ƈ��ŕ\���܂��B�l�X�̒u���ꂽ��������j�ɂ��A���@�̗L��l�͈قȂ��Ă����悤�ł��B �Ƃ���ŁA�P��╶�͂��ꂼ��T�^�I�ȈӖ��Ƃ�������h��������ӓI�ȈӖ��ɂ��s�J�e�S���[�t���`�����Ă��܂����A���@�����ӓI�ȕ\���͓T�^�I�ȕ\���Ƃ̗ގ����s�A�i���W�[�t����A�B�g�s���^�t�@�[�t�⊷�g�s���g�j�~�[�t�ɂ���đn�o����܂��B�u�ނ͑䕗�Œ�̉Ԃ����Ȃ��Ă��܂����v�Ƃ������A�T�^�I�Ȏg���\�����痣�ꂽ�\�������悤�ɁA�������͏⎖�ۂ��u��������Ƃ���v�\���Ŗ��t���悤�ƁA���X���t��n�����A����𑽋`�����Ă��܂��̂ł��B |
|
|
|
�@ �@ �@�u���g���b�N���o�v�@�����M�v�@�� ��l�� �q����̓��g���b�N�r ���t�I�݂Ȍ��ʓI�\�����g���Đl�𖣗�������A����������A�_�j�����肷��Z�p�u���g���b�N�v�́A�s�٘_�p�t��s�C���w�t�Ƃ������w��Ƃ��āA���[���b�p�ł͒������I�Ɍ�������Ă��܂����B�������A���̈���ŁA�\�ʂ����̔������A�y���ȋ��U�̕\���ƁA�ے�I�ɑ������邱�Ƃ��悭����܂��B �����M�v���́w���g���b�N���o�x�́A�s��������\���̋Z�p�t�A�s�|�p�I�\���̋Z�p�t�Ƃ��čl�����Ă����u���g���b�N�v���A�s�����I�F���̑��`�t�Ƃ����V���Ȏ��_�ő��������A�u���g�v�A�u�B�g�v�A�u���g�v�A�u��g�v�A�u�֒��@�v�A�u�@�v�A�u�ɏ��@�v�Ƃ�������̏C���@��������Ȃ���A�ǎ҂ɂ��̖{���I�ȈӋ`�𖾂炩�ɂ��Ă���܂��B �u���g�v�ƌ����u�`�̂悤�Ɂv�u�`�݂����ȁv�Ƃ������t���t������g�ŁA�u�B�g�v�ƌ��������������t���t���Ȃ���g���ƁA����̎��Ƃł͏K����������܂���B�ł��A���̖{�ł͂����ے肵�܂��B�ǂ�����ގ����Ɋ�Â�����g�\���ł���_�͓����ł����A�u���g�v�Ƃ́A�u�Ⴂ���̐l���A������ї���u�O�̂悤�Ȋ����ŗ����Ď������Ă����v�Ƃ����悤�ɁA�ǎ҂����܂ŕ��������Ƃ̂Ȃ��ގ������Ă��đz���������g�ł���A�u�B�g�v�Ƃ́A�u�v���m�点�Ă�낤�A�N�̔����������̉G�������Ɓv�̂悤�ɁA�u����=�������l�v�Ɓu�G=�X���l�v�Ƃ����A�ǎ҂ɗ����ς݂̗ގ������g������g�ł���ƌ����܂��B �ގ������g���������ς��u�B�g�v�ɑ��āA�u���g�v�Ƃ����̂́A�\������ΏۂɊW���A���̓�����\�����̂őΏۂ�����������\���ł��B���鏗�̎q�𖼑O�ŌĂԂ̂ł͂Ȃ��A���̓����I�ȗאڕ��u�Ԃ�����v�ŌĂѕ\������A�ꍑ�̐��{�����̌����u�z���C�g�n�E�X�v�ŕ\�������肷��̂����̗�ł��B �u���g�v���A�ΏۂɊW����ʂ̑��݂Ō���������̂ɑ��A�u��g�v�͑Ώۂ̏�ʊT�O�≺�ʊT�O�ɕς��Ē���\���ł��B�u��v�̂��Ƃ��u�������̂��~��v�ƌ�������A�u�H���v�̂��Ƃ��u�l�̓p���݂̂ɂĐ�����ɂ��炸�v�ƌ������肷��̂����̗�ł��B �����̃��g���b�N�́A�Ώە����i���������Ƃ̂Ȃ��ҒB�ɁA���̎p�����A���ɓ`���邽�߁A�s�����I�F���t�̂��߂Ɂs���`�t���ꂽ���̂ł����A�₪�Ē蒅���A���p��╁�ʂ̒P��ɓ]���܂��B�@������Ȋw�܂ŁA���B�̎g�p���錾�t�̋N����H���Ă݂�ƁA���̂قƂ�ǂ͋��U�E���g���b�N�Ƃ��Ēa���������̂��ƋC�Â���������܂���B |
|
|
|
�@ �@ �@�u���g���b�N�F���v�@�����M�v�@�� �@��܉� �q�F���̂��߂̕\���r ������N���ɓ`���������A�`���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�����̒��̎������炻��ɂӂ��킵���\����T���A�ł��A�����\�����t���Ȃ��Ȃ�������Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͂����N������̂ł��B����́A�����̌�b�̕n��䂦�ɐ����鎖�Ԃł��邩������Ȃ����A�����������{��̓��팾��̒��ɂ܂��Y�����錾��������������������܂���B����Ȏ��Ɏ������́A�����������Ă����b��g�ݍ��킹�A����ɗ����ł������ȃ��^�t�@�[�Ȃǃ��g���b�N���g���ĕ\�����悤�Ǝ��݂܂��B ����ł��A��͂茾�t���o�Ă��Ȃ���A��b�̏ꍇ�Ȃ��u�E�E�E�v�ƁA��������ł��܂����ƂɂȂ�܂��B�k�h�m�d��`���b�g�̎��́A�����ʂ�u�E�E�E�v�Ƒł����ނ��Ƃ����X����܂��B���������u�E�E�E�v�ɂ����w��̃��g���b�N�����t�����Ă���A�u�ِ��v�ƌĂ�Ă��܂��B�������̐l�����A���B�Ɠ��l�Ɍ�������Łu�E�E�E�v�ƂȂ��Ă���l�q��\���Z�@�ł�����܂����A��������l�\�꒟�u�_�B�v�̂悤�ɁA�����Ė{���������������A�ǎ҂̑z���Ɉς˂郌�g���b�N�̂��Ƃł�����܂��B �������Ȃ��A�����͌��Ȃ��u�ِ��v�ɑ��āA�u�����ł��Ȃ��A�����ł��Ȃ��A�����ł��Ȃ��A�v�Ɖߏ�Ɍ��t����ї��Ă�u���߂炢�v�Ƃ����̂����g���b�N�̈�ɐ������܂��B����͔����������������炸�Ɏ������Ŏ����玟�ւƎ�芷���Ȃ���Y�ލs�ׂɎ��Ă��܂��B����������́A�u�����̓`���������Ɓv�ɊY������\����������Ȃ��Ƃ����ȑO�ɁA���������u�`���������Ɓv�����Ȃ̂������ɕ������Ă��Ȃ���Ԃ��Ƃ������܂��B�������́A���t�ɂ��\���Ō`����߂���܂ŁA������F�����邱�Ƃ��o���Ȃ������Ȃ̂ł��B ����N�w�҂̍����M�v�́A�u���g���b�N�\���v�̑��ҁu���g���b�N�F���v�ŁA���B�̔F���ݏo�����߂Ɍ���\��������A�����́A�����ɑ���F���̎d����\���̂����t���Ǝw�E���܂����B �u�]�g�v�A�u�Δ�v�A�u�`�����v��u�t���v�A�u慚g�v�A�u����v�A�u�Î����p�v�Ȃǂ̃��g���b�N�́A�ߑ�̍�����`�E�Ȋw��`�I�ȏ��q�̎v�z�Ɍ����A�i�D���ĉߏ�ɖ��p�ȏ����t����Z�@�ƍl������悤�ɂȂ�܂����B�������A���g���b�N���g��Ȃ��{���I�E�W���I�ȕ��@�Ɋ�Â��L�q�ƍl��������̂��A�@�I�����A�Ȋw�I������F�����邽�߂̈�̃��g���b�N�ɉ߂��܂���B ���@�Ƃ������t�̐��x�́A�s���S�Ȑl�Ԃ̌���Ő��E�����H�v�̐ςݏd�˂��A�������Ă����Z�@�Ȃ̂ł��B |
|
�@ |
|
�@ �@�w�q�g�̌��t�@�@�B�̌��t�x�@��Y���@�� �@��Z�� �qAI�̌��t�̎d�g�݁r �@ �ŋ߁A�`�h�̔��W��g�߂Ŋ����邱�Ƃ������Ȃ��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�v���O���~���O���ł��Ȃ��Ă��v�����v�g�Ƃ������ʂ̌��t�œK�Ȏw�����o����A���b�Ŋ�]�̉摜�≹�y������Ă���鐶���`�h�����ł͖����ŒN�ɂł��g���܂��B�܂��A���R���ꏈ��������b�������f�o�s�́A�r�e��i�ɕ`����Ă���悤�ȃR���s���[�^�Ƃ̎��R�ȉ�b��̊������Ă���܂��B �`�h�Ɠ���I�Ɏ��R�ȃR�~���j�P�[�V�������Ƃ������K�ꂽ�悤�ɂ������܂����A����ł́u�`�h�Ɏd����D����v�A�u�`�h���l�Ԃ��Ă��܂��v�A�Ƃ������s���̐���������܂��B����ȍŋ߂̏ɑ��A����w�҂̐�Y�����͒����u�q�g�̌��t�@�@�B�̌��t�v�̒��ŁA�`�h�����t��a�����@�ƁA�l�Ԃ̌��t�̕s�v�c���A����x���ߒ����čl���Ă݂邱�Ƃ��Ă��Ă��܂��B �`�h�́A�l�Ԃ������ʂ̉摜�≹���̃f�[�^���A�s�N�Z���̐F�R�[�h��ʎq�����ꂽ���g���Ƃ��ē�i�@�Ő��l�����A���̐��̕��сE�g�ݍ��킹�̓��v�f�[�^�����������o���āA�摜�≹�y�����܂��B ���t�ɂ��Ă��A��ʂ̕��̓f�[�^����A�C�ӂ̒P��̎��ɑ����m���̍����P�����ׂĐ������Ă��������ł��邽�߁A�l�Ԃ̘b�̈Ӑ}�⎩���̌����e�𗝉����Ă���ƌ�����̂��A�Ƃ����_�ɂ��Ă͋^�₪�����Ă��܂��B �`�h�����̐��҃A�����E�`���[�����O�́A�@�B�̒m���Ɋւ��āA�`���[�����O�E�e�X�g�ƌ���������@���Ă��܂����B���镔���̒��ɋ@�B�Ɛl�Ԃ��ҋ@���Ă��āA�����̊O�ɂ���l�Ԃ����̎҂ƕ����ʼn�b�����܂��B�O�̐l�Ԃ��A��������b���Ă��鑊�肪�l�ԂȂ̂��@�B�Ȃ̂���ʂł��Ȃ��Ȃ������A�@�B�̎d�g�݂��ǂ�Ȃ��̂ł���A���̋@�B�͒m���������Ă���ƌ�������A�Ƃ����̂����̔�����@�ł��B ��������������@�ɂ͔[���ł��Ȃ��l������ł��傤�B�ł��A�������Ȃ��Ƙb���Ă���N�����A�`�h�Ɠ����悤�Ɋm���I�ɑÓ��ȒP��̕��тŌ��t��A�˂邾���̃A���h���C�h�������Ƃ��āA���̌��t���s���R�łȂ���A����̌��t�����_�������M�ɁA�l�Ƃ��Ă̋^�O�͎��ĂȂ���������܂���B ������邱�Ƃ́A�`�h�͐l�Ԃ�����ꂽ���t�̃f�[�^���w�K���Ȃ���Ό��t���g���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B����́A�������������Ă������߂̃R�~���j�P�[�V�����Ɏg���A�����Ă������߂̈Ӗ������߂�ꂽ���t�ł��B�܂��A�Ӗ��̐��l���͂ł��Ă��܂���B |
|
|
|
�@ �@�w�x�[�V�b�N�������@�x�@�ݖ{�G���@�� �@�掵�� �q�������@�����r �u�l�Ԃ͂Ȃ�������l���ł���̂��v�Ƃ������Ƃɂ��čl���邱�Ƃ́A�l�ԂƑ��̓����̈Ⴂ���Ȋw�I�ɖ��m�ɂ��悤�Ƃ��鎎�݂ł��B�l�Ԃƃ`���p���W�[�͈�`�q�Ō���ƈ꥓�O�������Ⴂ�������A�ꥌ܁��Ⴄ�E�}�ƃV�}�E�}�����߂������������Ƃ���Ă��܂��B�ł��A�`���p���W�[�ɐl�Ԃ̌�����o�������鎎�݂͐������Ă��܂���B �`���p���W�[�Ɍ��炸�A���̓����Ⓓ�������R�~���j�P�[�V�����͎�荇���܂����A�����ɂ͌�����o������⚓�肪�g���Ă���̂ŁA���t�������Ȃ��Ƃ͌����Ȃ���������܂���B�������A�l�Ԃ̌���ɂ́A���̓����ɂ͖�������������܂��B���ꂪ�A���@�ł��B�`���������e���ƂɈقȂ�t���[�Y��p���Ă���ƁA�\���ł�����e�͒P��̐��Ő�������܂����A���@������A�P����ɑg�ݍ��킹�邱�Ƃ��ł��A���ʂ���̕\�����\�ɂȂ�̂ł��B ���́A�l�Ԍ���̓����ł��镶�@���A�����I�ɔ]���ɐݒ肳��Ă��邽�߁A�l�Ԃ̗c���͌��t���g����悤�ɂȂ�̂��Ə����āA����w�Ɋv���������炵���l�����A�m�[���E�`�����X�L�[�ł��B �`�����X�L�[�́A����ȑO�̌���w���P�ꓯ�m�̑̌n�Ȃǂɂ��Č������A����l���̎d�g�݂̓u���b�N�{�b�N�X�ƌ��Ȃ��Ď�舵���Ă��Ȃ��������Ɍ��Ă����ƂŁA����w�Ɍ��炸�A�]�Ȋw�A�F�m�Ȋw�A���B�S���w�Ȃǂ̔��W�ɂ��e�����y�ڂ��A��\���I�ő�̌���w�҂ƌ���Ă��܂��B ���̗��_�A�������@�Ƃ́A�c�������܂ꎝ�������Օ��@�ƌĂ�錴���̒m���ɏ]���āA���͂Řb����錾����K�����Ă����Ƃ������̂ł��B���ꂼ��̌���͓��R�Ȃ��當�@����b���Ⴄ�킯�ł����A���������Ⴂ�͊��̕ϐ��Ƃ��đ������܂��B���E�ɂ͘Z��ȏ�̌��ꂪ����܂����A�S�Ă̌��ꂪ���ʂ̒萔�������̂悤�Ȃ��̂��Ƃ�����A�q�������͂��̒萔����ɂ��A��̓I�ȉp�����{��ɐڂ��邱�Ƃŕϐ���F�����A����ɉ����ăX�C�b�`����Ă����܂��B�Ⴆ�Ήp��Ɠ��{��ł́A�����ƖړI��̏���A�O�u���⏕���ȂǕt����̑O��̈ʒu���t�ł����A�����\�������\���͋��ʂ��Ă��܂��B�����ŁA�c���͎��ɂ������ۂ̌���q�ϐ��r�ɍ��킹�ăX�C�b�`���ւ��Ȃ�������K�����A�₪�Ă͌����ɏ]���Ď�����������o����悤�ɂȂ�Ƃ����킯�ł��B �������A���̗��_�͖��J�Љ�s�_�n���ȂǂŁA�����̔��Ⴊ������Ă���A���Օ��@�̎��݂͋^���Ă����܂��B |
|
|
|
�@ �@ �@�u�s�_�n���v�@�_�j�G���EL�E�G���F���b�g�@�� �@�攪�� �q�����ƌ���r �@�@�q�l�Ԃ̐Ԃ����́A���̓����ƈقȂ�A���܂�Ȃ���ɕ��@�̒m���������Ă��邽�߁A��e�Ȃǂ��炲������ꂽ���̒m�������^�����Ȃ��Ă��A�����ɕ������o����悤�ɂȂ�B�r ����ō��̌���w�҂ƍl�����Ă���m�[���E�`�����X�L�[�����������́y�������@�����z�Ɋ�Â��A����w�́A���E�̗l�X�ȈقȂ錾��ݏo�����ʂ̌�������Օ��@��T�����Ă��܂����B�����āA��\���ȂǁA�l�Ԃ̌���ɋ��L����镶�@�̃��[��������ɖ��炩�ɂ���A����w�����łȂ��A����̔]�Ȋw��F�m�Ȋw�̔��W�ɂ��傫����^���邱�ƂɂȂ�܂��B �������A�u���W���̃A�}�]���ɏZ�ޏ��������s�_�n���ɂ��ĎO�\�N�ɋy�ԃt�B�[���h���[�N���s�����_�j�G���E�k�E�G���F���b�g�ɂ��A���̉����̍��{��h�邪������̎��Ⴊ���邱�Ƃ�����w�̐��E�Ɏ�����܂��B �s�_�n���́A�A�}�]���̎x���}�C�V�쉈���ɐ��̑������l�S�l�ȉ��̏��������ŁA����̕����Љ�Ƃ͑傫���قȂ镶�����`�����Ă��܂��B�ނ�̌���ɂ͐���\���P��͂Ȃ��A�E�⍶��\�����t�̑���ɐ�̏㗬���Ɖ������Ō�����`�������܂��B�F��\�����t���Ȃ��A�F�̓I�����W�F�̂悤�ȁu�`�̐F�v�Ƃ�������̕��ŕ\���܂��B�g�������Ȃ��A�@���I�ȋV�����Ȃ��A���E�ɂ��Ă̑n���_�b���Ȃ��A�����ɂ��Ă̊T�O������܂���B�������Ƃ̂Ȃ����͈̂�ؐM�����A���ڑ̌����ꂽ���̂������ނ�̔F�߂錻���ł��B���i��{�[�g�ȂǁA�O���̋Z�p�𗘗p�͂��܂����A���炻������o�����Ƃ��w�ԋC�͂Ȃ��A���������̕�����ς��悤�Ƃ͂��܂���B�H���̔��~�������A�D���Ȏ��Ɏ�ɍs���A�K�v�ȕ������߂��ĐH�ׁA���Ȃ���ΐH�ׂ��ɉ߂����A�ł��x���Ė�𖾂����܂��B�a�C��g���̎���Q�����Ƃ͂����Ă��A�����ɑ��ĕs������������A�ꂵ��͂��܂���B ���̌���ɂ́A�������@���l�Ԍ���ɕs���ȗv�f�Ƃ��������̋�\�����Ȃ��A�����Ɠ���������̒P����������܂���B�������A���ڑ̌��̖L���ȕ������邱�Ƃ͂ł��A�ނ�ɂ��������Ȃ��X�̐��삽���̘b�����܂��B�q���̋�ʂ�K�v�Ƃ��Ȃ��@�̂⋩�ѐ��Ō�荇�����Ƃ��ł��܂��B ���̌���́A�������ƕ����Ƃ������R������i���E���W���Ă������̂ł���A�������玩���������Օ��@���猾�ꂪ��������Ƃ����`�����X�L�[�̉����́A�����ɕ����ꂽ�̂ł����B |
|
|
|
�@ �@�@�u����̖{���v�@����ނ݁A�H�c����@���� �@���� �q�I�m�}�g�y�Ɖ��ے��r �u�p���p���v�u�o���o���v�u�R���R���v�u�S���S ���v�A�Ԃ�����߂Ɋo���錾�t�Ƃ��āA���E���̌���ɋ��ʂ��Ă���ƌ�������̂́A���̂悤�ȃI�m�}�g�y�ł���悤�ł��B�I�m�}�g�y�́A�u�R���R���v��u�p�`�p�`�v�Ȃǎ�ɋ[����̂��Ƃ��w���܂����A���{��ł́u�O���O���v��u���������v�ȂǗl�Ԃ�\���[�Ԍ��A�u�h�L�h�L�v��u���N���N�v�ȂNJ����\���[�����܂܂�܂��B �����́A���ۂɎ��ŕ�����������A���o��G�o�Ŋ������l���A�S�Ő����銴��Ƃ̗ގ����琶�܂�Ă������t�ŁA��b�̑S�������Ԃ����ł��A�����̑̂Ŏw���ΏۂƂ̓��ꐫ���ސ��ł���Ƃ��������������Ă��܂��B�@ �������A������\���[����Ȃ�܂������A���������Ȃ��l�Ԃ⊴��A�ǂ����ĐԂ����ɂ��ސ��ł���̂ł��傤�H���{��ɂ͉p��́u�k�v�Ɓu�q�v��A�u�a�v�Ɓu�u�v�̋�ʂ��Ȃ��悤�ɁA����ɂ���Ĕ������邱�Ƃ̂ł��鉹�C�͈قȂ�܂��B����ł��A�ċC���̈Ⴂ�ɂ��A�u�o�A�s�A�j�A�r�A�a�A�c�A�f�A�y�v�͑j�Q���Ƃ����Ċp�������ł��������A�u�l�A�m�A�x�A�q�A�v�v�͋����Ƃ����Ċۂ������_�炩���������C���[�W�����邱�Ƃ��A���E���̌���Ŋm�F����Ă��܂��B�ꉹ�́u�A�v�Ɓu�C�v���A��҂��O�҂̕������̊J�������傫�����߁A�u�J���J���v�Ɓu�L���L���v�̂悤�ɁA�O�҂��傫�������A��҂��s��������l�Ԃɂ����炷�悤�ł��B���������A�������鉹���̂̎��C���[�W�����ے��ƌ����A�Ԃ����ł��̂Ŋ������邽�߁A�[�Ԍ��[���̈Ӗ����ނ�ɂ��ސ��ł���̂ł��B ���B�S���w�҂̍���ނݎ��ƌ���w�҂̏H�c������̋����u����̖{���v�́A����̋N���̓I�m�}�g�y�ł���A���̌�`�ω����疼���A�����A�`�e���A�������h�����A�₪�ĉ��ƈӖ����藣����Ă������ƂŁA����̑̌n���i�����Ă����̂ł��낤�Əq�ׂĂ��܂��B �R�̐�ɐ��𐂂炵�Ă��̕R���O���O���ƁA�����n���̎������葱���闝�R�������ł��܂��B���̂悤�ɁA�������ۓI�Ȃ��Ƃ𗝉����悤�Ƃ��鎞�A�������͂���ƍ\���̗ގ�������̓I�Țg���𗘗p���܂��B���������A�̊��ł���g�߂ȃ��m�Ƃ̗ގ�������A�̊��ł��Ȃ����m�̐�����ސ����邱�Ƃ��u�A�u�_�N�V�������_�v�ƌ����܂��B����́A�Ԉ���Ă���\�����[���ɂ��鐄�_�ł����A�l�Ԃ��Ȋw�I�ȗ��_�����鎞�ɂ��A�c����������K�����鎞�ɂ��A���́A�����𗧂Ă�\�͂��s���ł��B ����̏K�������̐i�����A�̊��ł����̂��璊�ۂւ̉����̗ސ��ƁA���̏C���̌J��Ԃ��Ő������Ă���悤�ł��B |
|
|
|
�@ �@ �@�u����̋N���v�@�_�j�G���EL�E�G���F���b�g�@�� �@��\�� �q����̈�`�q�r �@�u�����l�ރz���E�T�s�G���X�̌���͂ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂ꂽ�̂��v�ɂ��āA���㌾��w�̎嗬�h�́A���N�O�̃A�t���J�ɐ������Ă����T�s�G���X��̒��ň�`�I�ˑR�ψق��N���A���@�������������b���ŏ��̐l�ނ��a�������̂��ƍl���Ă��܂��B ���̌���w�I�ȈӖ��ł̍ŏ��̐l�ށu����w�I�A�_���v�́A����̉�X�Ɠ��l�ɕ��G�ȕ��@�Ƃ��āA�������b�����ƍl�����܂��B�����Ƃ́A�ꕶ�̒��Ɏ�߂Ə]���߂�����A���C���̎��Əq�ꂪ�T�u�̎��Əq����]���Ă��镶�̂��Ƃ������܂��B�Ⴆ�A�u�`����́A�a����͂����Ɨ���ƁA�l���Ă���B�v�̂悤�ɁA����q�\���ɂȂ��Ă���킯�ł����A����͍X�ɁA�u�`����́A�a����͂����Ɨ���ƁA�l���Ă���ƁA�b����͐������Ă���B�v�̂悤�ɓ���q�\������������₷���Ƃ��ł��܂��B�������̌���́A���V�A�̊ߋ�}�g�����[�V�J�̂悤�ɁA����q�\�����ɑ��₷���Ƃ��ł��܂��B ���̂悤�Ȍ�����g�����Ƃ��ł����`�q���A�����l�ނ͋��L���Ă���A���̓����ɂ͂��ꂪ�����Ƃ����̂��A�嗬�h����w�̍l�����ł��B���̍l�����̔��Ď҂��A����ō��̌���w�҂ƌ�����`�����X�L�[�ł���A�ނ͂�����������q�\���̕��������镶�@�y���Օ��@�t�f�z���l�Ԃ̌������ʂȂ��̂Ƃ��A���G�Ő��k�Ș_���I�v�l���\�ɂ��Ă���̂��ƌ����܂��B �`�����X�L�[�̂悤�ɁA�l�Ԃ̌���Ǝv�l�̓��ʐ���M������l�����͈�ʂɃf�J���g��`�ƌ����܂��B�ߑ㍇����`�̕����l�E�f�J���g�́A��V�I�ɔ�����������������l�Ԃɐ^���𗝉��E�F����������ʂȔ\�͂Ȃ̂��Ǝ咣���܂����B����́A�Ñ�M���V���̓N�w�҃v���g���ȗ��̏@���I�M�O�v���g�j�Y���ɗR�����Ă��܂����A���Ă𒆐S�ɋߑ�I�Ȋw�Z��������l�Ȃ�N�ł��A���ӎ��Ɏ����Ă���펯�I�ȐM�O���ƌ����܂��B �������A�A�}�]���̐�Z�����u�s�_�n���v�̌��ꌤ���Œ����ɂȂ����_�j�G���E�k�E�G���F���b�g�́A�s�_�n����ɂ͕����\�����������Ƃ��w�E���A�`�����X�L�[��ᔻ���܂����B�����āA���̌�̒����u����̋N���v�ł́A�ˑR�ψق̈�`�q������������w�I�A�_���ȂǑ��݂����A�����l�ނɐ�s�����z���E�G���N�g�D�X�ȗ��́A�W�c�I��b�̒~�ςɂ�镶���I�Q�i�I�ȏ��i�����A�l�ނ̕��G�Ȍ�����`�����Ă����Ǝ咣���܂��B ��b���́A�Ӗ��s�m��Ȍ��t�̏W�c�I���ݕ⑫�ŕ��@�͐�������̂ł��B �@ |
|
|
|
�@ �@�u���������͉�������ׂ��Ă���̂��H�v�@ �R�Ɏ���@��؏r�M�@���� �@��\��� �q���������̌����r ����\�͂͗L�j�ȗ��A�l�ԂƑ��̓����������鋫�E�Ƃ��āA���グ���Ă��܂����B�������A����ł͌������i�݁A�~�c�o�`�̃_���X�ȂǁA�����������l�X�ȃR�~���j�P�[�V�����̎�i�������Ă��邱�Ƃ��m���Ă��܂��B���ɂ́A�T�o���i�����L�[�̂悤�ɁA�V�G�������ƒ��ԂɉR�����āA�a��Ƃ��߂��悤�Ƃ��铮���܂ł��܂��B ����ȓ��������̌���Ɋւ��錤���ɂ����ċߔN���ɒ��ڂ���Ă���̂��A��؏r�M���̃V�W���E�J���̌��t�ɂ��Ă̕ŁA�V�W���E�J�����P�ꂾ���łȂ��A���@���������������Ă��邱�Ƃ��ؖ�������؎��̒��q�́A���w��N���̍���̋��ȏ��ɂ����グ���Ă��܂��B�ނ͉��N�ɂ��킽���ĐX�̒��ŃV�W���E�J���̌Q����ώ@���A���̒����������g�������āA�u�w�r���I�v�u�^�J���I�v�u�J���X���I�v�ƒ��Ԃ����ɂ��ꂼ��قȂ�x���Ԑ�����点�邱�ƁA���̖������l�ԂƓ��l�ɃC���[�W�����N����P��ɂȂ��Ă��邱�ƁA�����āA�ꏇ��ς���ƈӖ����ʂ��Ȃ��Ȃ镶�@�ɑ����ĕ�������Ă��邱�������܂����B�P�ꃌ�x���ł́A���̓����ł��������P�Ȃ銴��̔��I�ł͂Ȃ��A�Ӗ���`����R�~���j�P�[�V������i�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͒m���Ă��܂������A���炭�l�Ԃ݂̂������Ă���ƌ���w�̐��E�ŐM�����Ă������@�̐����\�͂��A���̂悤�ɔ]�̏����ȓ����ɂ����邱�Ƃ��ؖ����ꂽ���Ƃ͋����ł��B �w���������͉�������ׂ��Ă���̂��H�x�́A�ސl���̌����҂Ƃ��Ē����ȎR�Ɏ��ꎁ�Ɨ�؎��̑Βk���ŁA���������̑��l�ŖL���Ȍ���\�͂�A���͂��ΓI�Ƃ͌����Ȃ��Ȃ����l�Ԃ̌���Ɠ����̌���̑��ΓI�ȍ��فA�����āA����̋N���ɂ��Ă̗��҂̍l�@��������Ă��܂��B ��؎��́A�����̌���Ƃ́A�����Ă������߂̊��ւ̓K�����ƌ����܂��B���ĂŎ�����V�W���E�J���͐����̊댯���Ȃ��A���ɖ�����荇�����Ԃ̌Q�ꂩ���������Ă��邽�߁A���̒P��͂������Ȃ����̂ɂȂ邻���ł��B�������A�����炵�̈����X�ɐ��ޒ������́A�V�G����̋��Ђ̉��A�����ɕK�v�Ȑ������P��݁A���t�̗̈��W�J���āA�݂��ɒ��ӂ����N�������Ă���̂ł��B ���̕��ׂƁA����ɑ��鋦�͂��A�Q��̒��Ɍ�����������悤�ł��B |
|
|
|
�@ �@�u�����E�n���L�v�@�P���̒m�b�̎��̘b��� �@��\��� �q�����E�_���E�����r �����̑n���L�ɂ́A�u�P���̒m�b�̎��v��H�ׂČ��߂ݏo�����l�ނ̑c���o�ꂵ�܂��B���㌾��w�̎嗬�̍l�����ł��A�����玵���N�قǑO�ɁA���@���ł����`�q���������ŏ��̐l�ރA�_���ƃC��������A���R�����ɂ�肻�̈�`�q���������T�s�G���X�����������c�����A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B���������݂́A����w�҃`�����X�L�[�ɗR�����邱�̐������@���_�̍l����ے肵�A�]�̒��Ɍ���ɓ����������ʂȂǂ͖����A����̈�`�q���A����w��̃A�_���ƃC�������݂��Ȃ��A�ƍl�����嗬�h�̐��͂������Ȃ��Ă��Ă��܂��B �w�s�_�n���x�̒��҃G���F���b�g�́A���Ă͌��l�ƌĂ�Ă����z���E�G���N�g�X�̒i�K�ŁA���łɌ���͎g���Ă������낤�Ǝ咣���Ă��܂��B�����l�ނƂ͌���{�̍��i���قȂ邽�߁A���l�̊�p���ŕꉹ��q���𑀍삷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������Ƃ��Ă��A�����I�ȑŐ��Ί�Ɖ��g�p���Ă����G���N�g�X�ɂ͕���������A�R�~���j�P�[�V������i�Ƃ��Ă̔���=����͂������Ƃ����킯�ł��B �܂��A�����̌��ꌤ�����i�݁A�������̚���͒P��ƕ��@������������ł��邱�Ƃ��A���{�̌����ҁA��؏r�M���ɂ���ďؖ�����Ă��܂��B�����A�l�Ԃ̌���Ɠ��������̌���ł͑傫�ȈႢ������ƁA��؎��͌����܂��B����́A�u���A�����ɖ������́v��`���������Ƃł��B���������̉�b�́A�ڂ̑O�ɂ��鎖���ɂ��āA���̑Ώۂ�m���Ă���ғ��m�̕�w���Ɍ��肳��Ă��܂����A�l�Ԃ̌��t�́A�ߋ��▢���A��ԓI�ɉ�������Ēm�o�������Ƃ̂Ȃ��b�ɂ��Ă��A�A�i���W�[���g���ď��q���A�`���������Ƃ��\�ł��B���ہA�����������t�Ƃ��Ď����Ă���m���̑唼�́A�����ł͎��݂��m�F�������Ƃ̂Ȃ����̂���ł��B ��؎��ƑΒk�����ސl�������ҁA�R�ێ��ꎁ�́A�g�̊��o�Ɗ���̋��L�������Ɛl�Ԃ̌���ɋ��ʂ�������ŁA�����ɂ͔����̋������܂܂��ƌ����܂��B�����āA�����ɉ����āA�o�����ꉻ����\�͂��l�Ԍ���̓����ŁA����邱�Ƃ���_�������܂�A������[�������܂�Ă����̂��낤�ƌ����܂��B �Ƃ���ŁA�_���������l�Ԍ���̐��E�ł́A�_���I�ɐ�������Δ����ɔ������u���Ă͂����Ȃ����v�����u���Ă������v�ɏo����P���̒m�b�������܂��B����ɂ�錴�߂̓o��ł��B |
|
|